
Sony Global Solutions Inc.
ソニーグローバルソリューションズ株式会社

Sony Global Solutions Inc.
ソニーグローバルソリューションズ株式会社

前職では金融機関のSIer企業にて銀行の情報システムの開発・保守を担当。 福岡へのUターンを機に2019年にソニーグローバルソリューションズに転職。 現在はソニー半導体SCM(サプライチェーンマネジメント)システムの保守および、次世代半導体SCMシステム開発プロジェクトに従事。
私は現在、Application Capability 2部門 Factory Solution部 ISS Solution課に所属しています。主な業務は、ソニーの半導体ビジネスで使用される基幹システムの保守・運用です。また、次世代基幹システムの構築プロジェクトにも参加しています。
当課は、社員7名とパートナー63名の計70名で構成されています。パートナーの内訳は、日本に20名、インドに30名、中国に11名、米国に2名と、非常にグローバルなチーム編成です。
システム保守業務ではアーキテクチャ領域を担当し、データベースやサーバーソフトなどのミドルウェアの保守・運用に携わっています。サブリーダーとして、チームメンバーの作業内容や手順の管理、業務アプリケーションを担当する他チームとの調整、ユーザーへの作業報告や説明を行っています。さらに、インフラ部隊との作業調整やコミュニケーションも私の役割です。
一方、次世代システムの開発では、メンバーとしてアーキテクチャの領域を担当するチームの一員として活動しています。そこでは、海外の出荷拠点で使用するバーコードリーダーやプリンターなどの環境構築、プロジェクト完了後の保守運用を見据えた運用ルールの検討と策定、インドチームとのコミュニケーションフォローを主に担当しています。
私が所属する福岡オフィスには、Factory Solution部の別の課に加えて、プロジェクトを専門で扱う別部署も拠点を構えています。オフィス全体の人数は、社員だけで約30人。インドからプロジェクト業務で来ているメンバーを含めると約60人が在籍しています。
社員のうち福岡出身は7〜8名程度で、大阪や東京などさまざまな地域から集まっています。オフィスには集中して業務に取り組む環境があり、会議も活発ですが、親しみやすいメンバーばかりで楽しい雰囲気があり、飲み会などもよく開いています。
私が仕事で大切にしているのは、「ユーザーが困らないようにすること」です。ユーザーからの問い合わせは、「PCの設定やアプリケーションが起動しない」といった基本的な問題から、インフラ周りの設定変更によって起動しなくなったケースなど多岐にわたります。これらにできるだけ早く返信し、ユーザーの負担軽減を心がけてきました。
また、メンテナンス作業の際も、失敗して関係者に迷惑をかけないよう、細心の注意を払って確認することをモットーにしています。
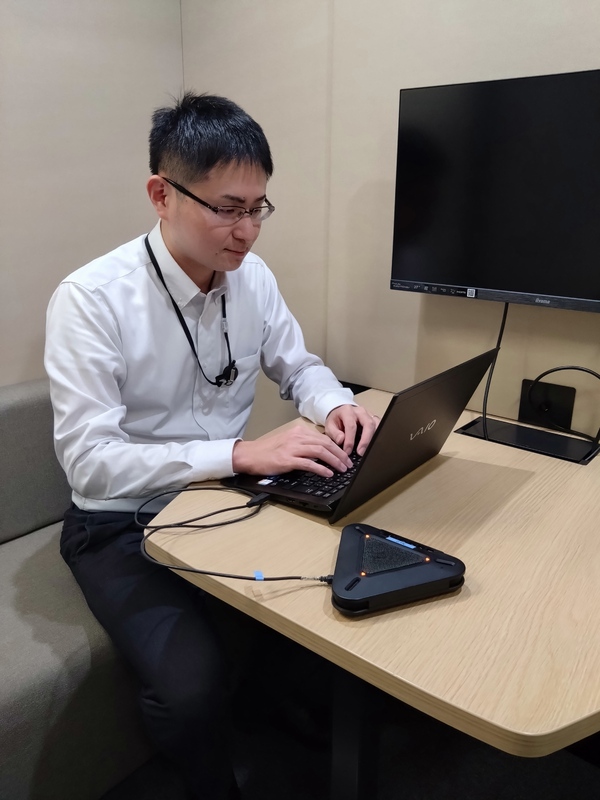
私がエンジニアとしてのキャリアを歩み始めたのは、大学時代の恩師との出会いがきっかけでした。その先生は経済学部の教授でしたが、「経済学だけで世界的な貧富の格差など大きな社会問題を解決するのは難しい。情報技術を活用して知見を広げ、意思決定を学ぶ必要がある」という考えを持っていたんです。その考えに強く共感し、先生のゼミに入って経済学と情報系の両方を深く学びました。
大学で身につけた知識を生かせる職業に就きたいと考えて選んだのが、金融機関のSIer企業です。入社後は、親銀行の情報システムの開発・保守部門に配属され、国内外の拠点から収集したデータを元に収益を管理する情報システムの新規構築プロジェクトに携わりました。
その後、収益管理サブシステムの高度化案件や保守を担当し、メインフレーム領域のリーダーとして設計から開発、テスト、移行までを一貫してリードする役割も任されています。
ところが、5年ほど経つと、将来的な生活基盤をどこに置くべきかを考えるようになったんです。家族のことも含めていろいろ検討した結果、福岡に戻りたいという気持ちが強まり、転職活動を始めることにしました。
当社を選んだ理由は2つあります。1つは、求められる役割や業務内容が自分の志向にマッチしていたことです。前職でIS関連の経験があったため、役割のイメージが持てた上に、アーキテクチャ領域の募集だったことも、私自身の興味と合致していました。
2つめは、福岡にいながらソニーグループの一員として働けること、そして東京と福岡で業務内容や待遇に差がなかったことです。福岡を拠点にITスキルを活かして、グローバルにインパクトのある仕事に携われる機会はなかなかありません。特に、ソニーグループのような大規模な組織のISとして、地方で働ける環境はとても魅力的でした。
入社後、前職とはまったく異なる環境に驚きました。1つは、新しい技術や変化への対応です。
前職に比べ、ソニーグループはAIやRPAといった新しい技術やツールを積極的に導入し、現場での活用を促進しているように感じます。こうした変化に対する前向きな姿勢は、エンジニアとしての成長にもつながっていると感じます。
もう1つが、グローバルな環境です。前職と違い、当社では海外のメンバーと直接仕事をする機会が多くあります。特にインドのメンバーとの協業では、お互いの前提知識や背景を理解し、明確なコミュニケーションを意識することの重要性を学びました。
この経験を通じて、私自身のコミュニケーション能力や異文化理解が大きく向上しています。

私にとって特に印象に残っている出来事は、2022年8月から翌年2月にかけて実施した基幹システムを構成する一部製品のバージョンアッププロジェクトを成功させた経験です。このプロジェクトは、日本、中国、インド、シンガポールのメンバーが関わるグローバルな体制の下、私は計画策定やミーティングの実施、進捗確認、上司への報告など、さまざまな役割を担当しました。
最大の課題は、システムを24時間停止する必要があったことです。普段は週末の4〜6時の2時間程度しか停止できないシステムを24時間も停止するとなると、ビジネスへの影響は計り知れません。もしトラブルが発生すれば、さらに長時間の停止を余儀なくされ、業務に甚大な影響を与える可能性もありました。
プロジェクト中、最も苦労したのが想定外の問題への対応です。インドのメンバーから「予期しない作業が必要になった」という報告を受けたり、シンガポールのインフラ部隊に急遽作業を依頼する場面が生じたりしました。
そんな時に心強かったのが、上司やチームリーダーの存在です。特に、ユーザーへの報告のタイミングや内容について的確な助言があったことは大きな力になりました。また、技術面でのサポートを受けたことでチーム全体への理解が深まり、スムーズな作業の進行につながったことも印象に残っています。
このプロジェクトを通じて、現在の仕事のやりがいを強く実感しました。まず、ソニーのビジネスに直接関わることができる点です。基幹システムの安定稼働に貢献し、1.6兆円の売上を誇る半導体ビジネスを支えているという確かな手ごたえがあります。
次に、さまざまなスキルを伸ばせる点です。チャレンジングな課題に取り組み、技術が大きく向上し、プロジェクト管理やコミュニケーション能力も磨かれました。これらの経験は、今後のキャリアにとって大きな財産になったと感じています。
さらに、グローバルな環境で働けることも魅力的です。英語力が大幅に高まり、国際的なプロジェクトに自信を持って取り組めるようになりました。
プレッシャーはありますが、常に高い水準が求められる環境で働く中で、日々成長を実感しています。また、努力や成果が適切に評価され、待遇にダイレクトに反映される点も大きな魅力です。

今後は、アーキテクチャ領域のプロフェッショナルとして更なる成長を目指しています。ソニーの半導体ビジネスで使用される基幹システムの安定稼働に貢献し続けることが目標です。
そのためにも、現在担当しているソニーの半導体SCM(サプライチェーンマネジメント)システムの保守業務や、次世代半導体SCMシステム開発プロジェクトでの経験を活かしながら、より高度な技術力と幅広い知見を獲得していきたいと考えています。
また、個人的には、仕事と家庭のバランスを大切にしていきたいです。柔軟な働き方を推進する当社の環境を活かし、出社とリモートのハイブリッドワークで効率的に業務をこなしながら、家族との時間を増やしていきたいと思っています。
入社して5年が経過し、当社で働く魅力を改めて感じています。ITスキルを活かしながら、ソニーグループの一員としてグローバルに働ける点です。私は転職を機に福岡に戻ってきましたが、入社前に想像していた通り、最先端の技術に触れながら仕事ができています。
福岡オフィスで働く魅力も感じています。オフィスの規模が比較的小さいため、社員同士の距離が近く、コミュニケーションが取りやすい環境です。時にはオフィスの外に出てプライベートな話題で盛り上がることもあり、良い気分転換になっています。
東京と業務におけるプレゼンスに差が無く、福岡がソニーの半導体ビジネスを支える中心的な拠点となっている事も重要な点です。Uターン、Iターンを考えている方にとって、非常に魅力的な環境だと思います。
また、多様性を尊重する文化があることも当社の大きな特徴です。国籍や人種を越えて協業する機会が多く、社員が持ち味を発揮することがポジティブに受け止められる風土が浸透しています。さまざまな価値観と出会い、自分の個性を活かしながら成長したい方、グローバルな環境に興味がある方にとって非常に働きがいのある職場です。
私自身、当社に入社して良かったと心から思っています。共にここで成長していける方と一緒に働ける日が来ることを楽しみにしています。
※記載内容は2024年10月時点のものです