
Sony Global Solutions Inc.
ソニーグローバルソリューションズ株式会社

Sony Global Solutions Inc.
ソニーグローバルソリューションズ株式会社

2013年入社マーケットユニット
経済学部 経済学科 出身
就職活動を始めた当初は、出版社と書店をつなぐ出版商社を中心に志望していました。そこで企業説明を聞いていると、書籍の在庫管理などに最新のシステムを使用しているという話をされることが多く、ビジネスの根幹を支えているのはシステムなのではないか、と考えるようになり、次第に他のIT企業やSIerにも興味を持つようになっていきました。選択肢が広がる中でソニーグローバルソリューションズ(以下、SGS)に惹かれたのは、採用面接の際にどこよりも私の話に耳を傾け、私のことを深く理解しようとしてくれたことが大きかったです。就職活動は時に企業と志望者の恋愛に例えられることがありますが、まさに私を尊重してくれる会社だと感じましたし、私自身、最も自分をさらけ出すことができた採用面接であったと感じたことが、SGSを選んだ一番の決め手となりました。
入社後、1年間のOJT期間を経て、ソニー不動産のWebサイトや、クラウドファンディングサイトをはじめとした新規事業のWebサイトの開発と保守運用業務を4年間ほど担当しました。特に新規事業の案件はリソースも限られていたため、専門領域以外のさまざまな業務を通して幅広い知識を身に付けることができ、その後の仕事にも役立つ非常にいい経験ができました。現在は主に、ソニーグループ株式会社の総務領域においてビジネスアカウントマネージャーとしてシステム企画などを担当しています。総務からの要望や相談に対して、現状や課題の整理をすることや、解決策として、ITソリューションが必要か否か、必要な場合は、既存のサービスで対応することができるか、あるいは新しいソリューションが必要なのかといった検討を行います。必要に応じてITソリューションの導入や新規プロジェクトの立ち上げまでを支援するなど、さまざまな形で、総務の問題解決をIT視点からサポートする仕事です。多くの時間を総務のかたと一緒に話し合いながら二人三脚で進めていますので、無事に問題が解決できたときの達成感も、なかなかうまくいかないときの歯がゆさも、お客様という関係性ではなく、同じソニーグループのメンバーとして共有できるところにやりがいを感じています。

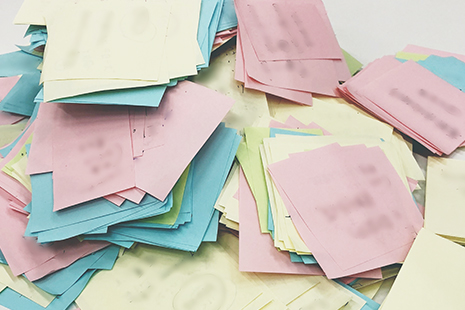
総務へのヒアリング
現状・課題の整理
ITソリューション・
その他解決策の検討
ITソリューション導入・
新規プロジェクト
立ち上げ支援など
SGSには、システム開発の下流から上流まで、そして幅広い領域に携わることのできるフィールドがあります。また、年々任される範囲が広がり、自分の役割や責任範囲も広がっていくため、着実に自分がステップアップしていることを実感できる環境だと思います。知識やスキルを身につけるたびに視野が広がっていくのが面白くて、気付けば勤続10年目を迎えようとしています。その途中で産休と育休も取得しました。ちょうど妊娠していた時にコロナ禍が始まりましたが、SGSではコロナ禍になる前から在宅勤務の制度が整っていたので安心して出産の準備ができましたし、今でも仕事と育児をバランスよく両立できています。日課である毎朝のランニングも続けられていますし、お休みの日は趣味のキャンプを家族で楽しんでいます。


今後も引き続き総務領域を担当するにあたり、業務知識を得ることはとても重要であると考えているため、直近では、総務の業務のひとつであり、企業の施設や設備を戦略的に管理する「ファシリティマネジメント」についての知識をより深めていきたいと考えています。いずれ機会があれば、経理や法務といった未経験の分野にもチャレンジして、さらに視野を広げていきたいです。最終的な目標はまだ模索中ですが、これからもさまざまな業務を経験することで、新会社や新規事業を立ち上げる際に必要な領域全般を、ビジネスアカウントの視点で網羅的に支えられるオールマイティーな人材を目指す道もあるかなと考えているところです。

これを読んでいる学生の皆さんにとっては学生時代の経験がすべてのように感じるかもしれませんが、今振り返ってみると、学生のころの経験は人生のほんの一部に過ぎず、社会人としての経験はその何倍も長く、幅広く奥深いものであることを実感しています。なので、私と同じように文系出身で現在ITやシステムの知識がなかったとしても、決して選択肢を狭める必要はありません。大切なのは、これから先社会に出た後で、「どんな自分になりたいか?」「どんなことをしていきたいか?」だと思いますので、是非その気持ちを大切にしてほしいなと思います。その気持ちを強く持っていれば、どんなことにも前向きに興味を持って取り組むことができると思いますし、周りは必ずサポートしてくれると思うので、ぜひ文系・理系を問わずたくさんの人に応募してきてほしいなと思います。
※掲載記事の内容は、取材当時のものです
※トップの写真は SSAP Open Innovation Village にて撮影